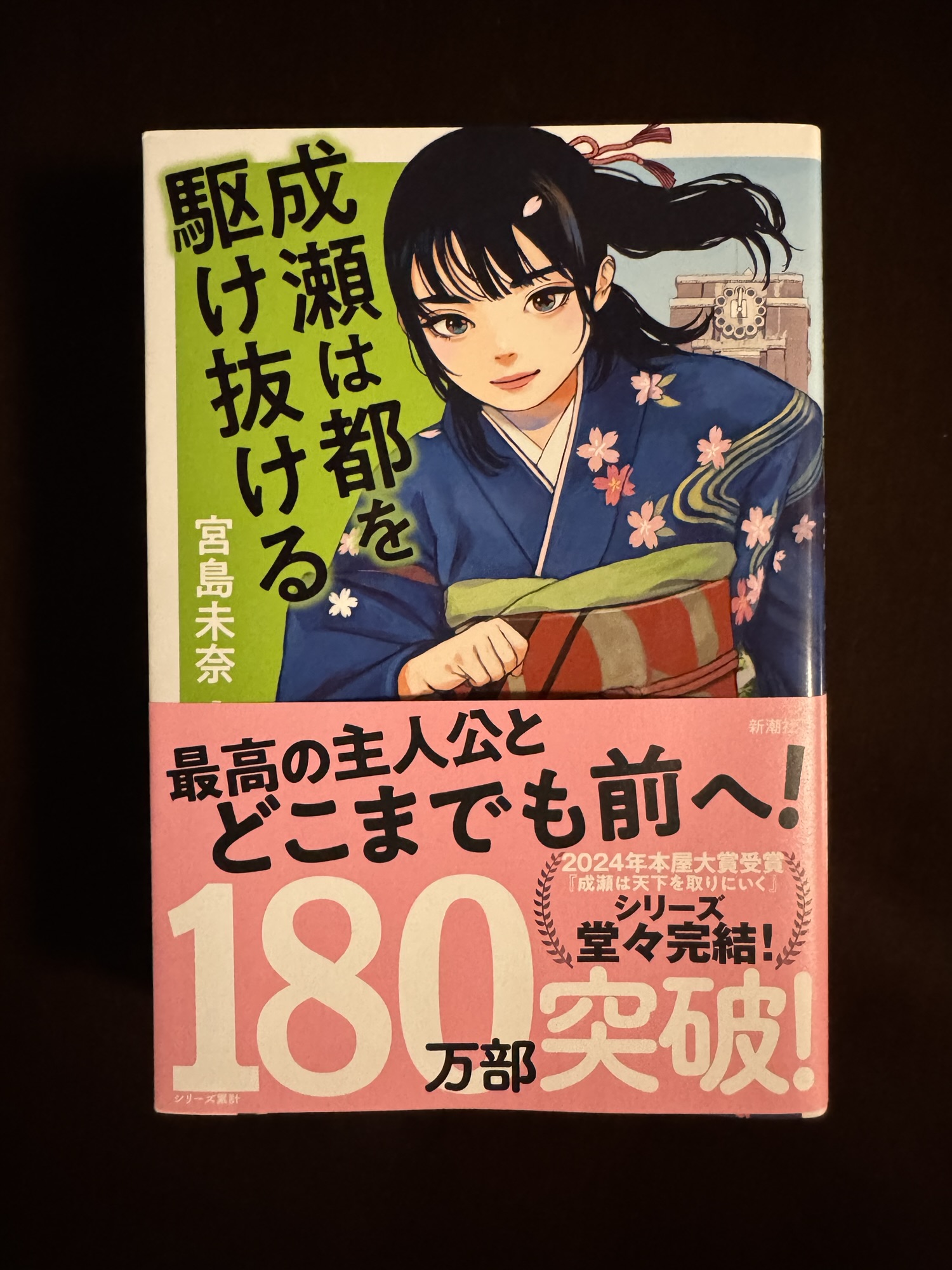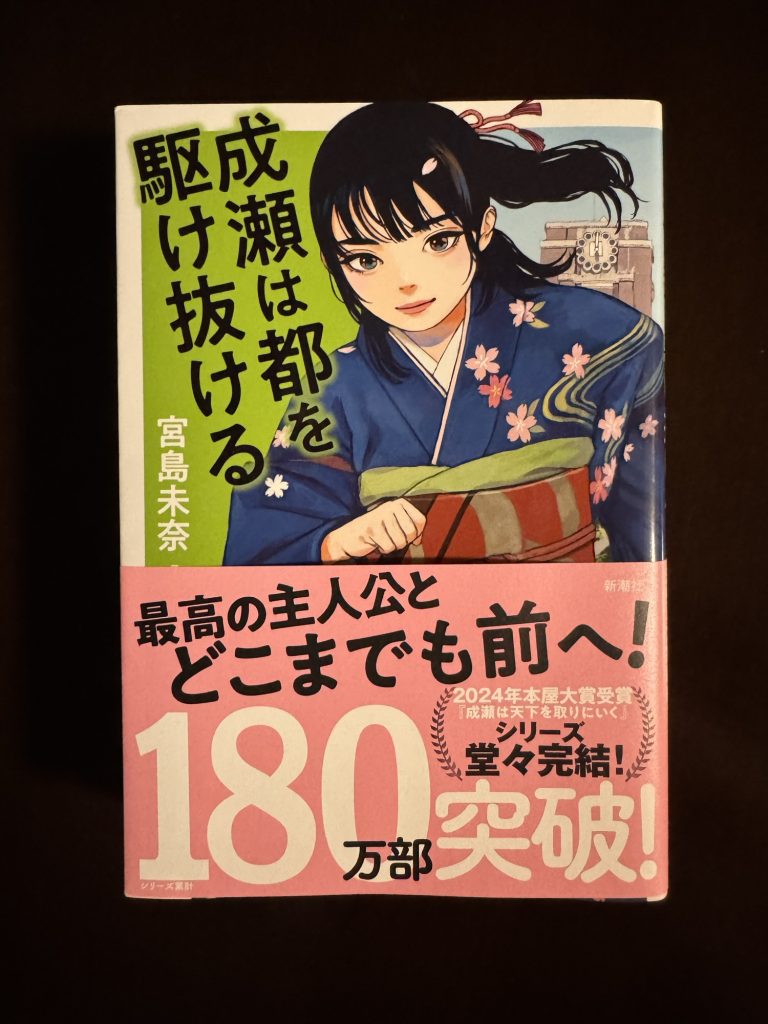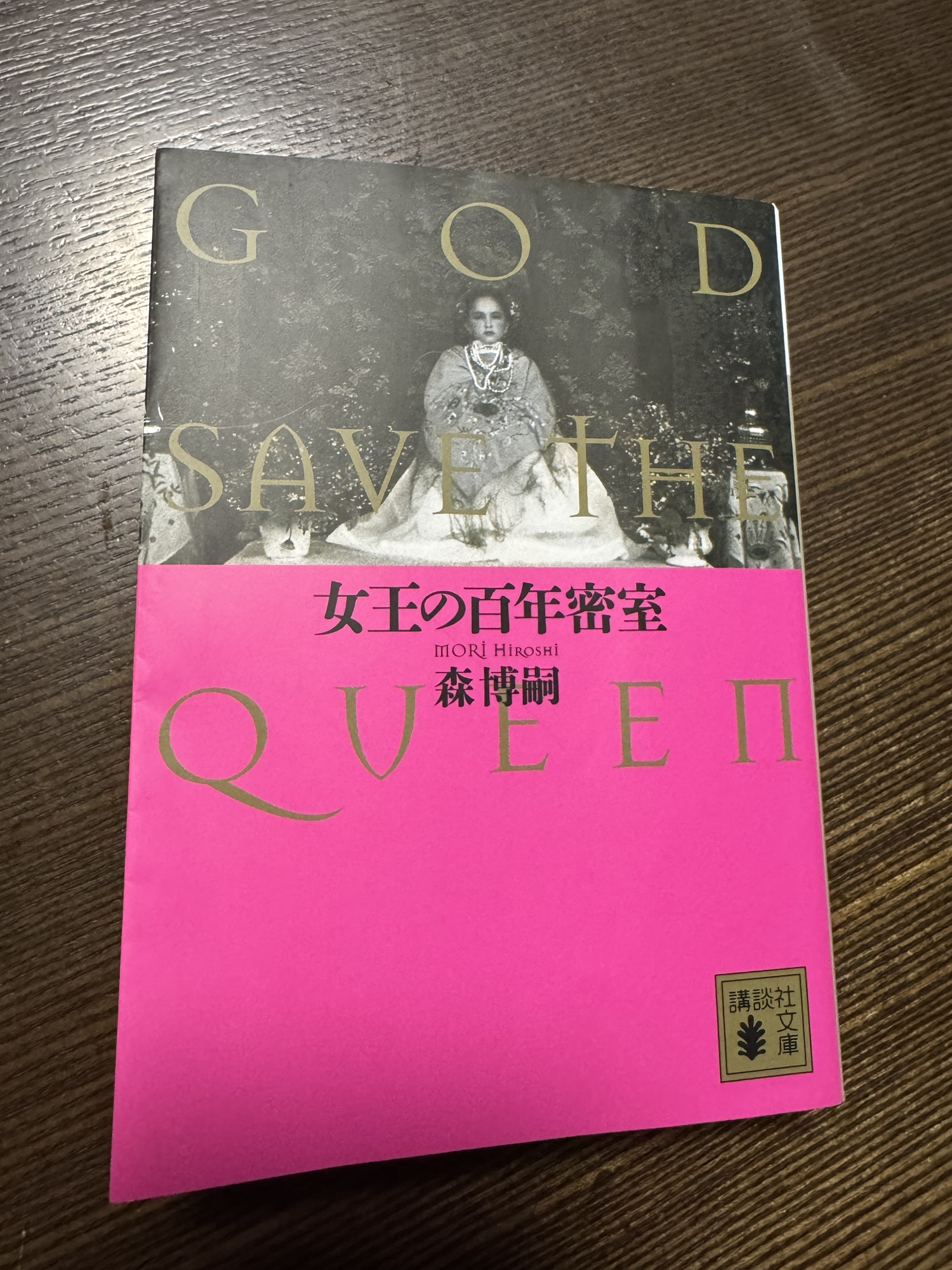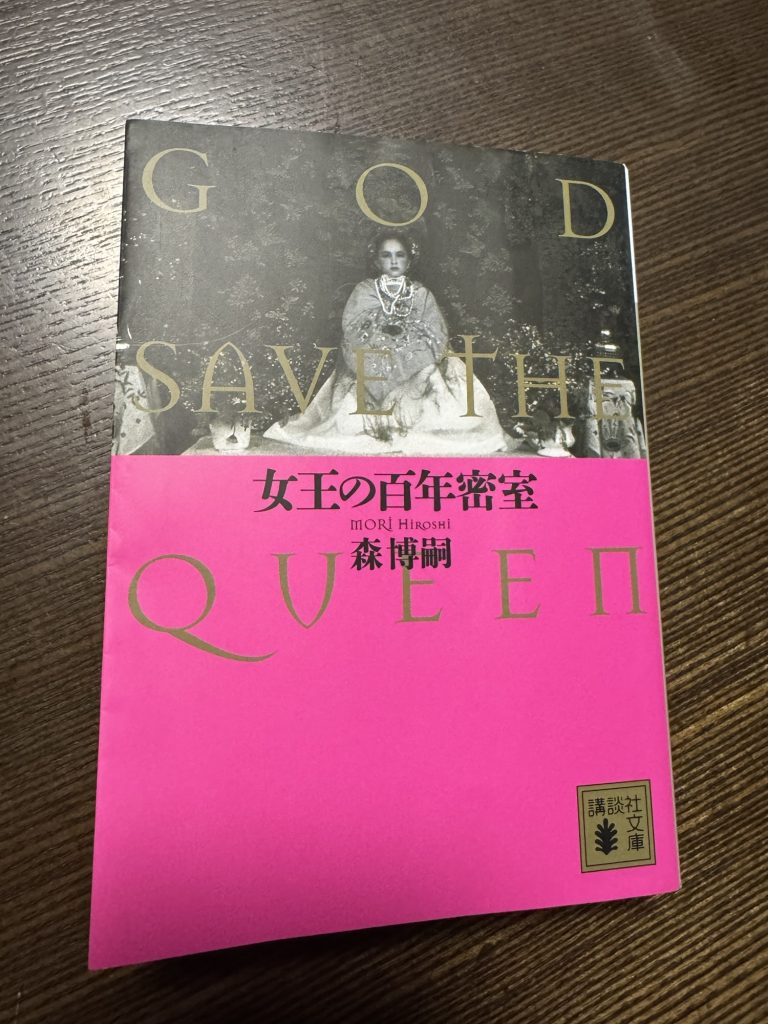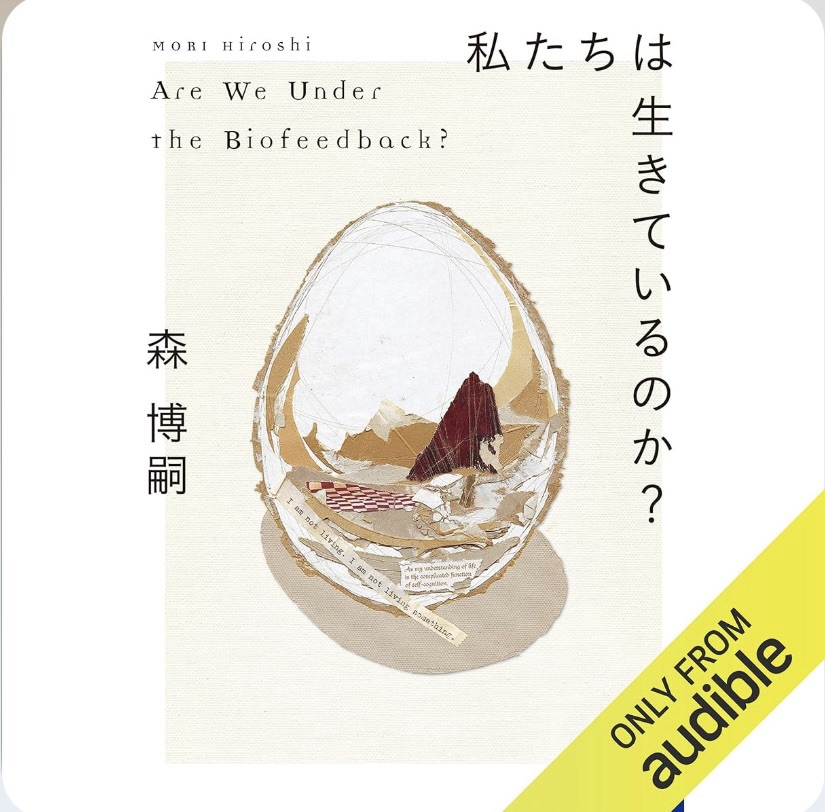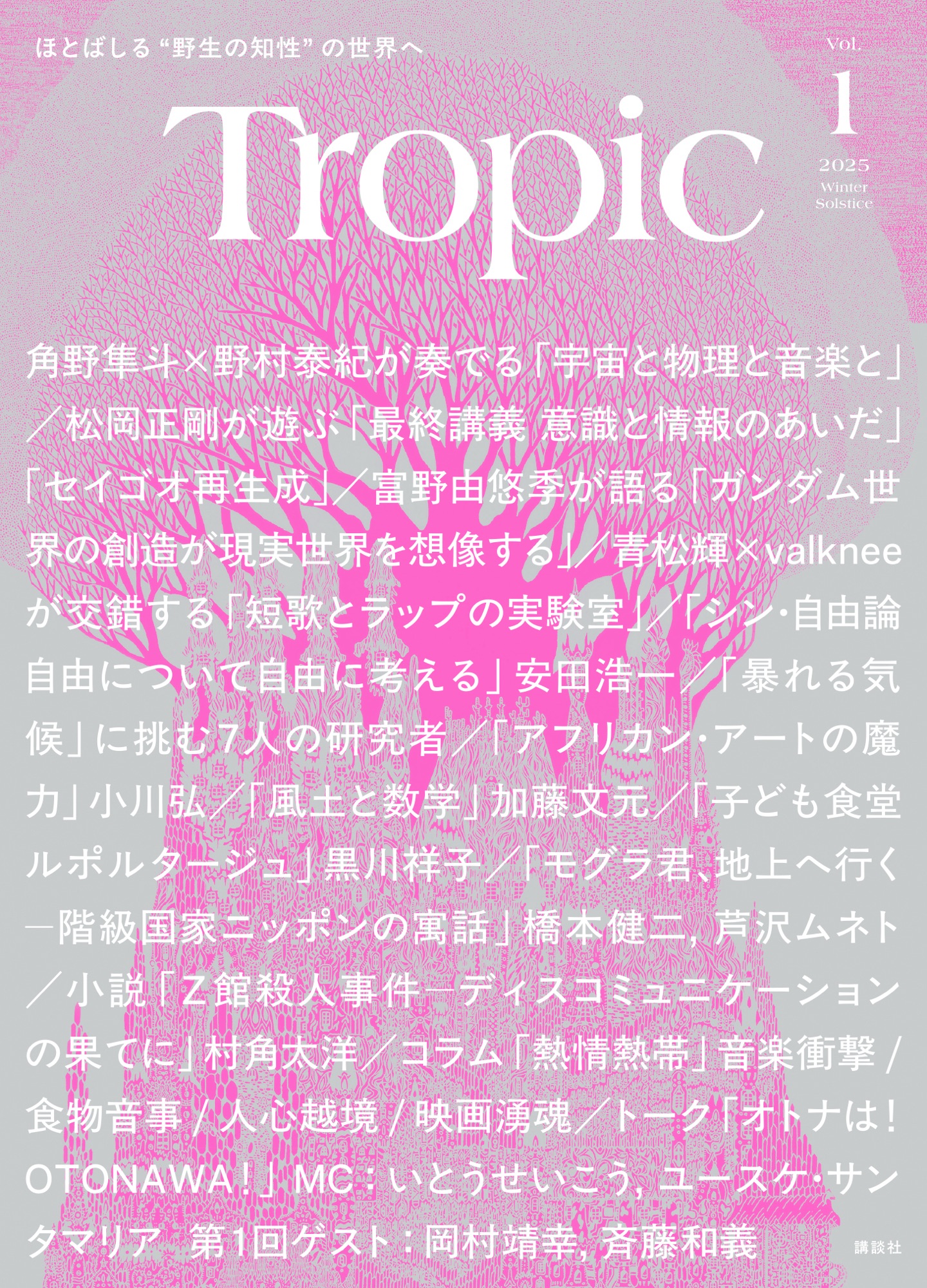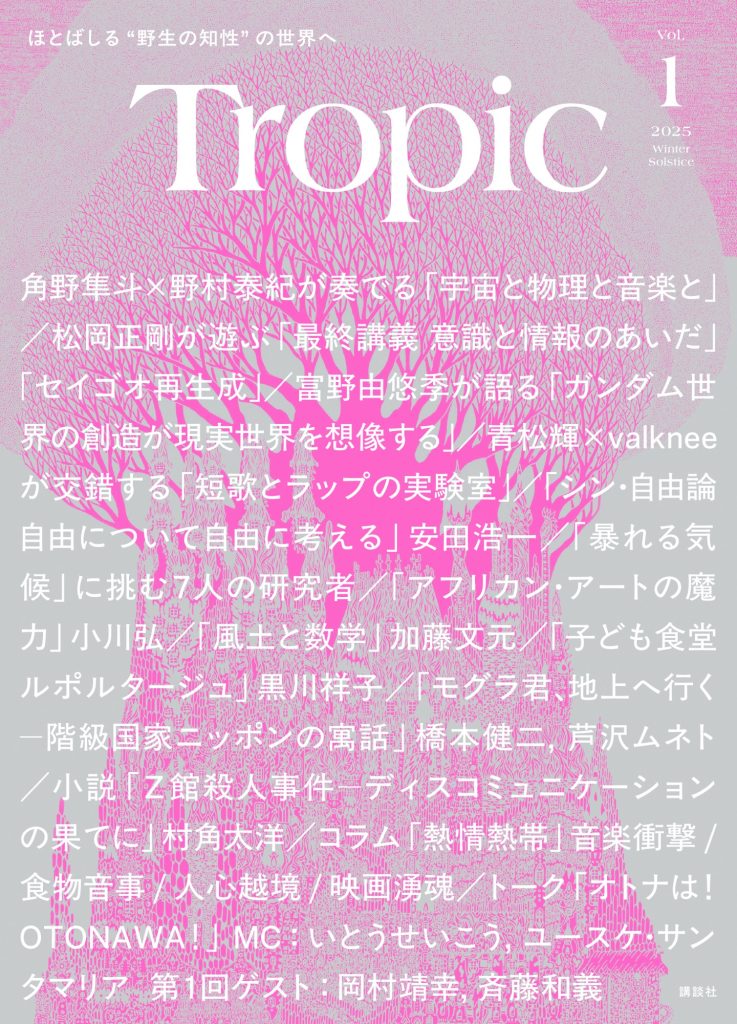パリを拠点に活動する李鎮雨(Lee JinWoo)による個展「潤(윤)」を開催いたします。本展は、2019年に当ギャラリーで開催された個展以来、4年ぶり3度目の開催となります。 李鎮雨は1959年ソウル生まれ。1983年に韓国の世宗大学を卒業後、1986年に渡仏し、パリ第8大学造形美術学およびパリ国立高等美術学校(材料学研究)を修了しました。 パリでの生活を始めた当初、李は困難な日々を送っていました。ある日、アトリエの片隅で芽を出した一粒の豆を見つけ、水とわずかな光のみで育つその生命力に感銘を受けます。この体験が、「水」を単なる素材ではなく、生命と記憶の循環を生み出す根源として捉えることへと発展しました。 李はこれまで、麻布に炭を載せ、幾層にも重ねた韓紙を鉄製のブラシで叩く独自の技法により、《泉》や《島》シリーズを制作してきました。この反復行為が生み出す独特の質感と、モノクロームの静謐な世界は高い評価を得ています。「水」をモチーフとする本展の新作シリーズでは、鉄ブラシに代わり、細い竹の棒を用いています。これにより、鉄ブラシの摩擦が生む力強い表現が一転し、より柔らかく繊細なリズムが画面に現れます。これは、作家が長年追求してきた「物質と精神の融合」という主題を、より身体的かつ直感的な次元へと深化させたものと言えるでしょう。